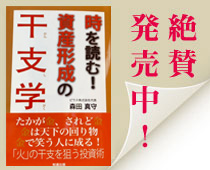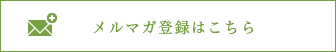※本講座は最初で最後の講座になります
講座名のとおりの内容をお伝えします。
しかし、「紙垂の作り方は動画サイトで既にある」と思うかもしれません。たしかにそのとおりですが、古くは古事記に出てくる紙垂(元はシラニキテ)は紙なのでしょうか…
本当の意味と造り方
古事記に出てくる時代には紙は貴重であり無いに等しい時代でした。その時代に有ったもので造ることであり作るとは少し意味が違います。少しややこしいですが、ご自身で使う紙垂をより縁起の良いものにして造る、古神道のある流派の興味深い造り方をお伝えします
形代を作る
大きな神社に行くと必ず形代があります。人の形をしたものや長方形の紙などです。しかし、これも古代からあったのでしょうか…紙がない時代に人々はどのようにして祈願を行ったのか…結論、古代から形代はありましたが紙ではありません。現代では教えにくいと云うか、少しお伝えするのを躊躇する怖さもあるのが古代の形代の作り方です。ポジティブに使えば素晴らしいものですがネガティブにも使えるのが難です
極めて異質であり、取り扱いを間違えると大変な事にもなると教わりました。非常に力のあるものですが慎重さも必要です
従って本講座は最初で最後であり、お申し込み時に受講をお断りする場合の人もいます。
ご興味がある方は、深い世界をのぞいてみてください
講座スケジュール
【日程】
2026/3/13(金) 10:00~20:00 (10:00~17:00 直会18:00~20:00)
※本講座には、その性質上、直会費用(お清め、食事等、含まれています)
【場所】
高知県高知市内 ※詳細は参加者に連絡します
※講座会場と直会会場と別となります
【参加費】
¥44,000/1名
【参加締切】
2026/1/20
【定員】
25名
【早期お申込み割引】
¥35,200 税込み
※2025/12/14までにお申し込み完了の方
【ご用意いただくもの】
半紙(練習用)コピー用紙(練習用)両適量
筆ペン(黒、朱)ハサミ(先端が尖っていないもの)
※費用は全て税込み
※定員になり次第締切となります
※本講座は日本の神道や仏教に否定的な方、新興宗教信者はお断りいたします